AIで課題解決!企業の事例から学ぶAI活用法
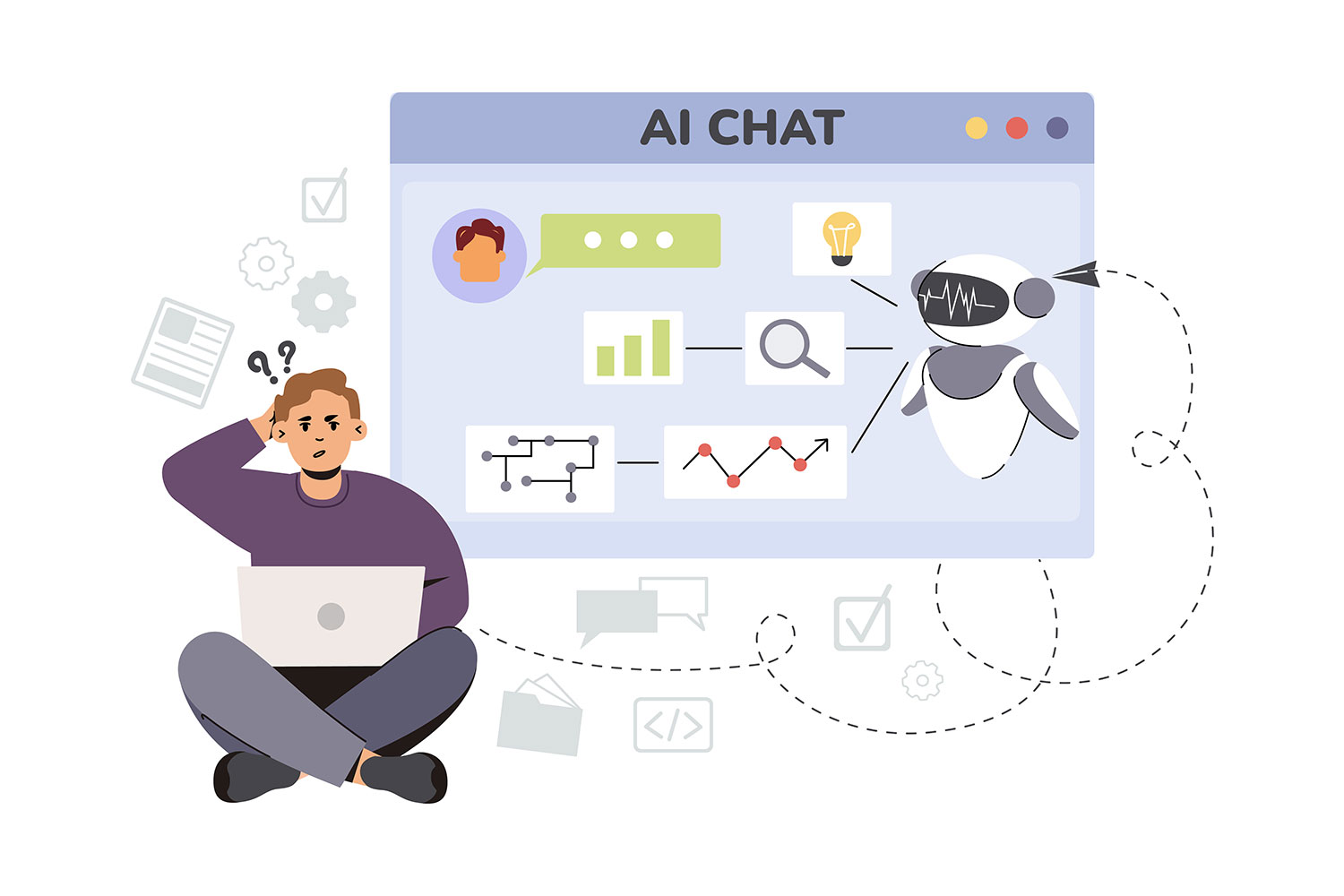
近年、AI技術の導入が急速に進んでいます。
生成AIをはじめ、画像認識や自然言語処理、予測分析など、多様なAI技術がさまざまな業種で活用され、業務効率化やサービスの向上に大きく貢献しています。
とくに2024年から2025年にかけては、ChatGPTなどの生成AIの普及により、多くの企業がAI導入を加速させています。
生成AIの進化は、限られた人員で多様な業務を担う自治体にとっても大きな可能性を秘めています。本記事では、民間企業の具体的なAI活用事例を紹介し、自治体業務での効率化やサービス改善に役立つヒントをお伝えします。自治体の皆さまがAI導入を検討する際の参考としてご活用ください。
令和4年6月 総務省 情報流通行政局 地域通信振興課:自治体における AI活用・導入ガイドブック <導入手順編>
人間の知能を模倣するAI(人工知能)とは?

AI(人工知能)とは、「Artificial Intelligence」の略で、人間の知的な作業をコンピューターでまねる技術のことです。人間の脳が行うような、言葉の理解や考えたり学んだりすることをコンピューターにさせることが含まれます。
ただし、AIにははっきりとした定義がなく、研究者によって考え方が少しずつ違うのが現状です。一般的には、「人間の知能を人工的に再現したもの」と考えられています。
自治体業務で活かせるAIの3つの力は識別・予測・実行
AIの機能は大きく分けて「識別」「予測」「実行」の3つに分類されます。
「識別」では、音声や画像、動画の認識や言葉の分析が行われます。
「予測」では、数値の予測やマッチング、利用者の意図やニーズの予測が行われます。
「実行」では、文章やデザインの作成、行動の最適化や作業の自動化が行われます。
今後は、識別や予測の精度がさらに向上することで、AIが使われる分野が広がると期待されています。また、複数のAIを組み合わせることで、実際に役立つ機能がさらに充実していくと考えられています。
AIと生成AIの違いとは?
AIとは、人間の知能をまねて判断・予測・分類・最適化などを行う技術のことです。多くの場合、既存のデータやルールに基づいて処理をします。AI(人工知能)と生成AIの違いは、「何をするためのAIか」という目的と機能にあります。
たとえば、スパムメールの振り分けや需要予測、顔認識、チャットボットの応答などが代表的な使い方です。
一方、生成AIはAIの一種で、文章や画像、音声、動画などの新しいコンテンツを作り出すことに特化しています。学習したデータをもとに、人が作ったような自然な表現を生み出すのが特徴です。具体例としては、文章を作るChatGPT、画像を作るDALL·E、動画を作るSoraなどがあります。
小売業のAI活用による業務の効率化と個々にあったサービスの提供

小売業では、AIを使った需要予測やおすすめ情報の提案(レコメンデーション)、価格の調整、チャットボットによる問い合わせ対応、画像認識による店舗運営の支援などに活用されています。
これらの技術は自治体の仕事にも活用できる可能性があります。たとえば、需要予測を使えば、地域の公共サービスの利用状況やイベントの参加者数を事前に予測でき、必要な準備がしやすくなります。おすすめ提案の仕組みを応用すれば、住民の情報に合わせて子育て支援や健康診断、地域のイベントなどの案内を個別に届けることができ、サービスの利用を促進できます。
価格の最適化技術は、公共料金の見直しや補助制度の設計にも役立ちますし、24時間対応のチャットボットを導入すれば、申請や予約などの案内を自動で行うことで、職員の負担を減らしながら住民への対応を充実させることができます。また、画像認識の技術は、公共施設の点検や防犯カメラの映像から異常を早期に見つけることにも使えるため、トラブルの早期発見・対応に役立ちます。
このように、小売業で実際に使われているAIの仕組みを自治体に取り入れることで、業務が効率化されるだけでなく、住民一人ひとりに合わせたサービスの提供が可能になり、より住みやすい地域づくりに貢献できると期待されています。
民間企業によるAI活用事例|アパレルブランドA社
アパレルブランドA社では、AIを活用して高度な需要予測と在庫の最適化を実現しています。過去の販売データや気象情報、イベントのトレンドなどを総合的に分析し、最適な商品投入量を計画することで、品切れ防止や過剰在庫の回避に成功しました。その結果、在庫コストの削減と廃棄ロスの削減を同時に実現しています。
また、AIチャットボットは、顧客の購入履歴や好みに基づいて商品や着こなしを自然な言葉で提案し、パーソナライズされた買い物体験を提供しています。ECサイトや店舗の在庫情報と連携し、より精度の高いユーザーサポートを実現しています。
自治体での活用例としては、防災備蓄品や公共施設の物品管理、チャットボットによる住民サービス案内やFAQ対応が考えられます。さらに、データを連携してリアルタイムに情報を活用する仕組みや、住民視点に立った対応体制の構築は、自治体が持続可能で効率的な行政運営を目指すうえで非常に参考になる取り組みです。
民間企業によるAI活用事例 |ECモールB社
B社のECモールでは、生成AIや大規模言語モデル(LLM)を活用したサービスで、出品者の情報入力や改善提案を自動化し、出品作業を大幅に効率化しています。「AIアシスト」は売れ残った商品の情報を分析し、タイトルや説明文の改善案を提案することで、出品の質を高め売上アップにつなげました。また、「AI出品サポート」は商品写真をアップロードするだけで、カテゴリ選定や説明文の自動生成ができ、数ステップで簡単に出品が完了します。
自治体での活用例としては、申請データの整合性チェックや改善案の提示による業務支援が挙げられます。文書テンプレートの情報をアップロードするだけで、AIが提案を自動生成し、観光案内や子育て支援情報など複数のデータを整理して自然な文章を作成することも可能です。これにより、行政パンフレットやガイドサイトの運用効率が向上します。また、地場産品のECサイトにも応用が可能です。自治体の業務効率と住民サービスの質を同時に高めることが期待されます。
製造業のAI活用による業務の効率化やコスト削減

製造業では、AI(人工知能)を使って「機械の故障を事前に見つける」「品質チェックを自動で行う」「効率の良い作業スケジュールを立てる」などの工夫が進んでいます。これらの工夫より、人のミスが減ったり、コスト(お金)が抑えられたりしています。
このようなAIの使い方は、自治体の業務にも応用できます。たとえば、道路や橋、水道などの点検にAIを使えば、壊れる前に異常を見つけられるかもしれません。また、施設の清掃や巡回をロボットに任せることで、人手不足の解消にもつながります。災害時の避難や物資の配布にも、AIで最適なルートや方法を考えることで、よりスムーズな対応が可能になります。製造業でのAIの使い方をヒントにすることで、自治体も住民サービスを向上させながら、業務の効率化やコスト削減を目指すことができます。
民間企業によるAI活用事例 |飲食業C社
飲食業C社では、AIやIoT、ロボットを使って製造ラインを効率化し、品質向上やコスト削減を実現しています。具体的には、生産中の無駄を減らしたり、作業を自動化して安定した製造を行ったりしています。
このような技術は、自治体でも応用可能です。たとえば、防災施設や公共設備の状態をAIで監視して劣化を早めに予測したり、備蓄品の管理を効率化して無駄な廃棄を減らしたりすることができます。
また、定型的な窓口業務や申請手続きを自動化すれば、職員の負担が軽減し、住民サービスの質も向上します。リアルタイムで状況を把握し、将来を見越した対応ができることで、よりスマートで効率的な行政運営が可能になります。
物流業のAI活用による配送効率化と自動化で負担軽減

物流業では、AIを活用して配送ルートの最適化や需要予測による在庫管理、倉庫内でのロボット制御、荷物の仕分けや追跡の精度向上、自動運転やドローン配送による労働力不足への対応などが進んでいます。
これらの技術は自治体でも活用でき、災害時の支援物資の効率的な配送や備蓄品の管理、自治体のごみ収集ルートの最適化や公共施設の物資管理の省力化、過疎地への医療物資配送などに役立てることができます。AIによるリアルタイムなデータ分析や最適経路の自動提示を活用することで、業務の効率化と職員の負担軽減が期待できます。
民間企業によるAI活用事例|物流業D社
物流業D社では、物流センターや倉庫間の商品移動をAIが自動で最適に判断する「需要予測モデル」を使い、いつ・どこから・何を・どれだけ運ぶかを効率よく決めています。これにより発送作業の無駄を減らし、業務をスムーズにしています。
また、物流現場ではAIロボットが商品を集める作業を手伝い、生産性を大きく向上させるとともに、働く人の負担も減らしています。さらに、社員全員が使える対話型のAIツールで、文章の要約や企画書作成なども効率化しています。
これらの技術は、自治体の物資管理や施設内作業、職員の業務支援にも役立ちます。リアルタイムの需要分析や作業の自動化を活用することで、住民サービスの向上と行政コストの削減を両立させる、新しい行政運営のモデルとして参考になるでしょう。
金融業のChatGPT活用による時間削減と生産性の向上

金融業では、AIを使って顧客対応の効率化、リスク管理、データ分析、業務の自動化が進んでいます。たとえば、チャットボットや音声認識を活用した問い合わせ対応により、窓口業務の負担を軽減しています。また、AIが大量の取引データを分析し、不正検知や信用リスクの評価を高精度で行うことで、リスク管理を強化しています。
自治体に応用する場合、住民からの問い合わせ対応をチャットボットで自動化し、職員の負担を減らせます。加えて、住民の申請内容や履歴を分析して不正を早期に発見したり、公共サービスの利用傾向を把握したりして効果的な政策立案に生かすこともできます。
さらに、福祉支援や助成金の審査にAIを導入することで、公平かつ迅速な判断を支援し、住民サービスの質向上に貢献します。
このように、金融業でのAI活用は、自治体の業務効率化やリスク管理、住民サービスの充実に役立つ多くのヒントを提供しています。
民間企業によるAI活用事例|金融業E社
E銀行では、生成AIをさまざまな業務で活用しています。新しい経営計画では、300件以上のAI活用プロジェクトを支援する体制を整え、AIやデータ基盤の強化に力を入れています。とくに法人営業では、営業資料や提案書を自動で作成することで、新しいお客様の獲得数が大きく増えました。
また、AIツールを使い、大量の情報収集や分析作業の時間を約1万時間も減らし、職員の負担を大幅に軽くしています。
これらの技術は、自治体でも活用できます。申請の案内文や報告書、窓口で使う文書を自動で作成したり、住民向けの施策案内をより正確に作成したりすることが可能です。また、住民のニーズや過去の施策の効果をAIで素早く分析できるため、効率的な行政運営と質の高い住民サービスの両立に役立ちます。
これからの未来とAI活用

日本は少子化や人口減少、高齢化という大きな課題に直面しています。総人口は今後も減り続け、2040年には約1億1,000万人になると予測されています。また、高齢者の割合が増え、社会保障費も増加していく見込みです。こうした中、自治体では限られた人員や予算で、これまで以上に質の高い住民サービスを提供していくことが求められています。
そのため、総務省が令和元年度から始めた「自治体AI共同開発推進事業」では、AIやビッグデータを活用して自治体業務の効率化や地域課題の解決を目指しています。とくに、これまで十分に活用されていなかった分野でのAI導入に向けた実証実験も進んでおり、自治体にとって効果的なAI活用のモデルづくりが進んでいます。
今後、AI技術を取り入れることで、自治体の業務はより効率的になり、住民の多様なニーズに応えるサービスの質も向上します。AIは自治体の強い味方となり、地域の未来を支える重要なパートナーになる期待されています。
内閣府:選択する未来 -人口推計から見えてくる未来像-/-「選択する未来」委員会報告 解説・資料集-
まずは相談を!AI活用でどんなことができるのか聞いてみよう
ここまで各業界を代表する企業におけるAI技術の活用例をご紹介してきました。企業各社がAIを活用する背景には、単にトレンドだからというわけではなく、人手不足や技術継承に対する課題意識があります。そしてこの課題感は、全国の自治体でも共通しているのではないでしょうか。
当社は「官民協働による地域活性化」をコンセプトに、DX事業を通じた、現場の課題解決をご支援しています。
たとえば自治体の窓口業務をサポートする「わが街AIチャットボット」などがあります。
「AIを使って業務を効率化したい」「AIで公共サービスをもっと良いものにしたい」「何から始めたらいいかわからない」という方は、是非お気軽にお問い合わせください。
わが街AIチャットボット
問い合わせURL








