【Yのコラム①】本質から考える自治体DX―官と民で創る未来のかたち

はじめに
近年、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉が行政分野においても広がりを見せています。しかしながら、自治体におけるDXの導入は依然として限定的であり、十分に浸透しているとは言いがたい状況にあります。その背景には、「DX」という概念自体の理解が曖昧であることや、単なるデジタル化と混同されている実態があります。
ここでは、DXとはそもそも何を指すのかを改めて整理したうえで、その本質が単なるデジタル化ではなく、組織や仕組みそのものの見直しであることに注目し、どうすれば“真のDX”につながるのかを考えてみたいと思います。
そもそもDXとは
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタルの力を活用して、組織・サービス・業務・働き方といった“あり方そのもの”を変革することを指します。
「トランスフォーメーション」は英語で「変化」や「変容」を意味し、単なる技術の導入にとどまらず、根本的な構造の見直しを伴うものです。DXという言葉を聞くと、システムの導入やペーパーレス化といった取り組みを思い浮かべるかもしれません。しかし、これらは“デジタル化”に過ぎず、業務の本質が変わっていないケースも多く見られます。場合によっては、「紙の方が便利だった」「余計に手間が増えた」といった現場の不満につながり、結果としてコストや時間の浪費につながり、本来の目的を果たせていないと言えるでしょう。
真のDXとは、デジタルを単なる手段として活用しながら、「人」「組織」「価値」の在り方に向き合い、より良い未来を創造していくことにあります。自治体が目指すべきDXは、技術導入そのものではなく、その先にある価値の創出なのです。
とはいえ、いざDXに取り組もうとすると、どうしても「システムを導入すること」や「デジタル化すること」が第一に思い浮かべてしまうのも現実です。真のDXを実現するためにも、ここではデジタルを伴わないトランスフォーメーションの事例を参考にしながら、「真のDX」について考えていきたいと思います。
自治体事例
兵庫県神戸市

神戸市教育委員会は、2026年8月までに市立中学校すべての部活動を終了し、その運営を地域のスポーツクラブなどに移行する方針を決定しました。この背景には、少子化に伴う休部や廃部の増加、教員不足、そして教員の働き方改革の必要性など、さまざまな課題がありました。従来、部活動は学校の教師が顧問として指導するのが一般的でしたが、神戸市はこの固定観念を見直し、部活動の本質である「子どもたちの成長支援」に焦点を当てました。そのうえで、地域の大学や民間企業、NPOなどと連携し、部活動を学校外に開く取り組みをスタートさせています。市教育委員会はすでに、生徒たちを受け入れる地域団体の募集を始めており、これは地域や社会の力を活用しながら子どもたちを支える、新たな官民連携のスタイルと言えるでしょう。
これは、単なる制度変更にとどまらず、「学校の役割とは何か」という本質への問い直しでもあり、クラブ活動の“あり方そのもの”を変えた、教育分野におけるトランスフォーメーションの好例です。
神戸市:部活動の地域移行
熊本県庁
熊本県庁では、DXの推進にあたり、専任組織の設置とその組織の生産性を高めるための環境整備が不可欠であると判断し、「デジタル戦略局」を新設。併せて、オフィス改革にも着手しました。
具体的には、職員の座席を固定せず、業務内容や気分に応じて自由に座席を選べる「フリーアドレス制」を導入。さらに、ペーパーレス化によってできた書庫の空きスペースを活用してミーティングルームを新設しました。これにより、業務の効率化や生産性の向上に加え、職員同士のコミュニケーションも活性化することに成功しました。まさに働き方改革の実現へとつながっています。
従来の「固定席」や「紙中心の業務」といった前提を見直し、オフィスのあり方そのものを変えるという“トランスフォーメーション”を通じて、DXが目指すべき「働き方の革新」に一歩近づいた事例と言えるのではないでしょうか。
【公募型プロポーザル】熊本県庁舎勤務環境改善フリーアドレス導入実施業務委託 – 熊本県ホームページ
愛知県安城市
安城市では、「図書館」を単なる本を読む施設として捉えるのではなく、まちのにぎわいを生み出す拠点として位置づけ、再構築に取り組みました。新しい図書館には、250席のホールやカフェ、市民課の窓口などを併設。さらに、隣接地には273台分の立体駐車場のほか、スーパーマーケットやカルチャースクールなどを備えた商業棟も整備されました。加えて、「にぎわい創出」のための様々な空間も設けられており、広場では定期的にマルシェなどのイベントが開催されています。ホールではコンサートや映画上映、エントランスでは展示即売会や作品展など、多様なイベントが連日行われ、市民が気軽に足を運べる場所となっています。
こうした取り組みの結果、図書館の利用者は大きく増加し、これまで利用率が低かった家族連れの来館も目立つようになりました。「図書館とは静かに本を読む場所」という固定観念を取り払い、新たな価値を創出した事例と言えるでしょう。単なる図書館の整備ではなく、まち全体のにぎわいを生み出す取り組みとして、大きな成果を上げています。
安城市中心市街地拠点施設アンフォーレ公式ホームページ
新しい価値の創出
これまで紹介してきた事例に共通しているのは、表面的な変化ではなく、「本質を見極め、新たな価値を創出している」という点です。DXに取り組む中で、システム導入やデジタル化といった“手段”が、いつの間にか“目的”にすり替わってしまう場面は少なくありません。しかし、それでは単に業務の手順が変わっただけに過ぎず、本来の目的である「人や社会にもたらす価値」は置き去りになってしまいます。
DXとは、技術を導入することではなく、その先にある“人の幸せ”や“豊かな未来”を創り出すことです。時代が変わり、社会のニーズが多様化する今だからこそ、自治体は一人ひとりが変革の担い手として、自分自身の仕事や組織の「当たり前」を問い直していかなければなりません。
DXはゴールではなく、よりよい社会を実現するためのスタートラインです。「変える勇気」と「本質を見極める目」を持ち、目の前の業務に小さな“トランスフォーメーション”を起こしていく。その積み重ねこそが、真のDXであり、未来を変える力となるのです。
最後に

ここまでデジタル技術に頼らない“トランスフォーメーション”の事例を通して、本質的な変革の在り方を見てきました。その中で、最も大切なことは、変革の主役が「人」「価値」、そして「未来への持続可能性」にあるという点です。目先のデジタル化にとらわれるのではなく、その先にある新たな価値を見失ってはならないのです。
そしてもう一つ、すべての事例に共通しているのが、「官民連携」の存在です。
神戸市では、子どもたちの成長を支える部活動に、地域や民間の力を取り入れました。熊本県庁は、民間企業と協働してオフィス環境を改革し、働き方そのものを見直しました。安城市は、図書館をまちのにぎわい創出の拠点へと再構築し、その実現に多くの民間企業が関わりました。
複雑で多様な課題に対し、自治体が柔軟かつスピーディに応えていくためには、その“あり方”自体をトランスフォームしていく必要があります。その鍵となるのが、官と民が手を取り合い、新しい価値を共に創り出していく姿勢です。
自治体の未来を変える第一歩は、「変化を恐れず、ともに創ること」、その歩みの先に、自治体が目指す持続可能で豊かな社会が広がっているのです。
筆者紹介
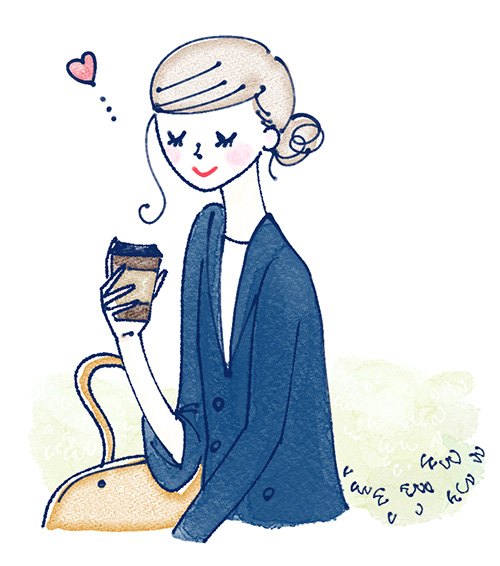
元自治体職員Y
面倒くさがりな性格だからこそ、市役所勤務中は、業務改善やDX推進に積極的に取り組んできました。楽しくチームで働くことが好きで、職員同士の交流イベントなども多数企画。現在はサイネックスに転職し、よりたくさんの自治体の支援をしたいと考えています。








