現在進行形で拡大中!自治体によるクラウドファンディングの成功事例

限られた財源で地域の未来をどう守り、活性化していくのか。人口減少などの課題が山積する中で、クラウドファンディングやふるさと納税など自治体の新たな財源確保と応援の仕組みが注目されています。プロジェクトに対する共感から始まる支援、個人や企業の寄付による目標金額の達成は、プロジェクトの実現に欠かせません。まちや住民の魅力を引き出し地域の課題を解決するために、どのようにクラウドファンディングを活用するべきなのでしょうか。本記事では具体的なクラウドファンディングの種類や自治体の取り組み、成功事例から実践方法までを解説します。読者の皆さんのまちづくりへの一歩に、ぜひお役立てください。
まずは基礎から。クラウドファンディングの種類
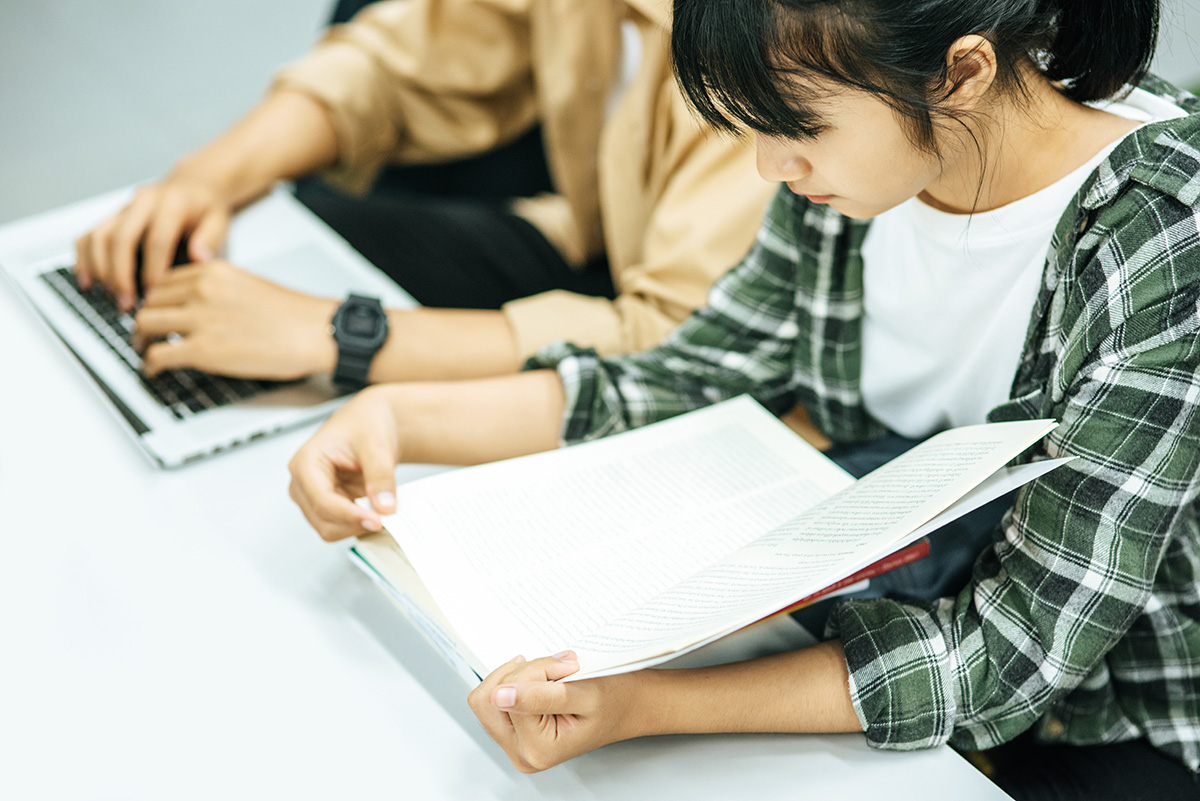
クラウドファンディングにはいくつかの種類があり、それぞれ資金調達や支援の方法に特徴があります。
融資型クラウドファンディング
融資型クラウドファンディングは、個人や企業が地域のプロジェクトや事業への資金供給を行い、リターンとして金利収入や元本回収を目指す仕組みです。通常のふるさと納税と違い、使い道がより明確で、自治体や事業者がプロジェクトごとに具体的な目標金額や内容を提示できることが特徴です。また、金銭的リターンを求めるため、支援者は事業採算性といった事業計画をしっかりチェックする傾向があります。
寄付型クラウドファンディング
寄付型クラウドファンディングは、地域課題や応援したい活動への共感が寄付の原動力になります。寄付なので金銭的・物品的なリターンはありませんが、お礼の手紙や写真などを贈る形となることが多いです。リターンに期待しない寄付の形を取ることもあり、寄付型のクラウドファンディングは寄付金の使い道が具体的で、かつ地域課題の解決につながることが明確であることが重要となります。
購入型クラウドファンディング
購入型クラウドファンディングは、その名の通り支援者が物品やサービスを購入する感覚で支援するクラウドファンディングの形態です。プロジェクトの成立後に返礼品やサービスが提供される、最も一般的なクラウドファンディングの1つです。地域産業や観光資源の発信、地元スポーツイベントへのサポートにも多く利用されています。プロジェクトの成立には目標金額に達しなければならないものが一般的ですが、支援者が1人でもいればプロジェクトが成立し、返礼品が発生する場合もあります。
株式投資型クラウドファンディング
株式投資型クラウドファンディングは、支援者が資金提供の対価として出資した企業やプロジェクトの株式を受け取る形態です。地域発の新規事業やまちづくりのスタートアップを始める際に有効です。事業が成功すれば投資リターンが得られる仕組みで、自治体も経済合理性をもった形で地域活性化につながる事業が行える可能性があるため、雇用創出や継続性の面でメリットがあります。一方で企業側からすると、出資者が無計画に多くなりすぎると合意形成にかかる手間が増えるため、株式投資を呼びかける対象者の基準を設けたり、募集する出資割合などをよく考える必要があります。
ファンド型クラウドファンディング
ファンド型クラウドファンディングは、複数の投資家から資金を募り、地域活性や文化事業、健康や教育など幅広い地域事業の運営資金に充てる仕組みです。金銭的なリターンを得ることが前提で、あわせて物品やサービスも受け取ることがあります。単なる金融商品ではなく、地域課題の解決に寄与する社会性が高い点が特徴です。融資型との違いは、融資型が金利形式でリターンが計算されるのに対して、ファンド型は事業の利益からの分配金としてリターン金額が決まります。
自治体のクラウドファンディングとは?
自治体によるクラウドファンディングは、地域活性化や課題解決を目指して住民や全国の支援者から資金を募るための仕組みです。プロジェクトごとに資金の使い道や地域の目標を明確に示し、寄付者は共感した自治体の取り組みに金銭的な形の支援を行います。
通常のクラウドファンディングとの違いは「社会性」と「地域性」
自治体によるクラウドファンディングと通常のクラウドファンディングで、基本的な流れに違いはありません。プロジェクトの目標設定、資金計画、クラウドファンディングのプラットフォームへの登録、広報活動、支援金対応などを計画的に進めることになります。
自治体の場合は、住民や地域企業との協力体制、地域課題や産業振興、観光や医療・教育への支援という社会的意義が大きい点が特徴的です。返礼品やリターンも自治体特有の産品や体験など地域性が高いものを用意しやすく、自治体主催であるため信頼感も高いです。
ふるさと納税とは明確な違いがある
ふるさと納税は、自治体への寄付を通じて返礼品と税金控除が受けられる制度ですが、資金の使い道について明確な説明は必須とされていません。ふるさと納税は地域貢献目的もありますが、節税の方法として利用している人が多い傾向があるといわれています。
自治体が行うクラウドファンディングは、資金を必要とするプロジェクトの明確な目的や使い道を公開し、共感した人から直接支援を集めます。そのため、節税目的よりも地域に貢献したい思いやプロジェクトそのものの事業性が重視される傾向があります。
近年はふるさと納税においても寄付金の使い道を指定できるため、クラウドファンディングと似たものになりつつあります。しかし明確に違うのは、クラウドファンディングが「資金を求めるプロジェクトの中身によって支援の是非が判断される」のに対して、ふるさと納税は「返礼品の内容によって是非が判断される」点です。
もっと詳しく!自治体ならではの疑問

自治体独自のクラウドファンディングは、プロジェクトの主体が自治体自身という点がポイントです。住民税や交付金といった歳入が財源ではなく支援金が財源となるため、「どのような事務手続きが必要なのか」「プロジェクトがうまくいかなかったらどうなるのか」などの不安があるかもしれません。
予算化する必要はあるの?
基本的に集める予定の支援金額を歳入、かかる経費を歳出として予算化する必要があります。自治体によりますが、クラウドファンディングで集める予定の金額を歳入予算とし、自治体が用意している何らかの基金への繰入金として計画するケースがあります。用途が指定された歳入であるため特定財源となります。
歳出については、クラウドファンディングのプラットフォームに登録する費用やPRにかかる費用、運用事業者へ委託する費用、返礼品がある場合はその費用などを歳出として予算化します。
目標金額に至らなかったらどうなるの?
クラウドファンディングには、目標金額に至らなかった場合はプロジェクトを実施しない「All or Nothing 方式」と、目標金額に達しない場合でも事業を実施する「All in方式」があります。
「All or Nothing 方式」の場合、目標金額に達しなければ支援者に支援金を返金することになります。しかし、自治体が支援者の一人ひとりの銀行口座に支援金を振り込んだりする手続きは非常に煩雑で実現が難しいため、事業者にクラウドファンディング運営を委託することがほとんどです。事業が成立した場合のみ支援金を歳入に計上し、成立しなかった場合は事業者が返金手続きを行います。
「All in方式」の場合は、目標金額に達しなくともプロジェクトが行われます。自治体としては返金手続きをしないことや、必ず業務を行うこともあり、事業者へ委託せず直営で実施する場合もあります。目標金額に達しない場合、足りない費用は自治体の財源から拠出することになりますが、支出の見直しは求められるでしょう。
「目標金額達成!」自治体クラウドファンディング成功・先進事例から学ぶ

近年、多くの自治体がクラウドファンディングを積極的に活用し、地域コミュニティに新たな資金循環を作り出しています。複数自治体の連携型プロジェクトや民間事業と一体となった運営事例も増えつつあり、地域の産業・スポーツ・観光・文化支援が広がりつつあります。このような多様な自治体プロジェクトの成功は、多くの共感・応援による新しい財源確保の仕組みとして他の自治体にも取り入れられ、今後もさまざまなプロジェクトを生み出していくでしょう。
福井県鯖江市のユニークな取り組み「新成人を祝うめがねのまち」
福井県鯖江市では、「めがねのまちから、成人式にふさわしい記念品を!」というキャッチコピーのもと、国産フレーム世界シェアを誇る地元産業を活かしたふるさと納税活用プロジェクトを展開しました。新成人にふるさとの技を誇るめがねを贈り、まちの魅力・地域産業の強みを全国に発信する取り組みです。
とあるクラウドファンディングのプラットフォームでは目標金額300万円に対して、約400万円が集まりました。寄付金は実績豊富で手厚いサポートのもと運用され、「寄付額自由」など斬新なコース設定で参加しやすさが向上しました。市民や応援者の声も前向きなものが多く、まちの活性化や文化発信、母校への誇りづくりにもつながっています。
埼玉県深谷市が届ける「障がいのある子どもたち」の夢への架けはし
深谷市のゆるキャラのふっかちゃん子ども福祉基金「夢の架けはし」プロジェクトは、深谷市が直接の運営主体となり、深谷市のゆるキャラと共に障がいのある子どもをサポートする取り組みです。
既存制度や法律で救済が難しい子どもたちにも支援の輪を広げ、地域住民をはじめ全国からの寄付が集まりました。とあるクラウドファンディングのプラットフォームでは目標金額の200万円を上回り、221万円が集まりました。
寄付金は、パラリンピック出場選手の競技用装具支援、スポーツ助成、難聴児の補聴器購入補助、心身障がい児の療育支援、iPad整備といった多様なプロジェクトに充当されます。ユニバーサルデザイン推進など、障がいの有無に関わらず誰もが夢をもち挑戦できるまちづくりを目指し、今後もプロジェクト資金は幅広く活用されます。返礼品には深谷市出身のパラリンピック選手のサイン入り木製置時計や箸などが用意されています。
佐賀県で挑んだ「どんな境遇の子どもも見捨てない」プロジェクト
佐賀県では、子どもの貧困という社会的課題に対処するため、ふるさと納税の仕組みを活用したクラウドファンディングを実施しました。「どんな境遇の子どもたちも見捨てない!佐賀県発の『子ども救済システム』」プロジェクトは、支援金の具体的な使い道を掲げたことで、多くの共感を集めた事例です。
「給食が唯一の食事」「修学旅行のためのお金がない」といったさまざまな貧困に置かれている子どもを支援するための運営資金に充てられています。とあるクラウドファンディングのプラットフォームでは目標期間内で目標金額の1,000万円を上回り、1,480万円の寄付が集まりました。これによって地域活動の充実と今後の継続的な支援体制構築に大きな弾みがつきました。
この事業は、一過性のものではなく慢性的な社会課題に継続的に向き合う枠組みとして、情報発信や自治体活動の広報としても高い効果を発揮しています。支援した子どもの人数も450人に達しています。運営主体は公益財団法人佐賀未来創造基金なので、自治体がクラウドファンディングの主体ではありませんが、佐賀県とも連携して事業運営をしており、佐賀県もふるさと納税の選択肢として採用するなどの支援をしています。
岡山県倉敷市のファンド組成を支援する「コネクトローカルプロジェクト」
ファンド型クラウドファンディングは自治体にとって大きな金額を集められる魅力がありますが、実際はまだまだ普及していません。理由は自治体がファンドの事業計画や財務状況を投資家に開示する必要があり、開示情報によっては住民情報や機密情報が含まれる可能性があったり、投資家からの自治体経営への干渉リスクがあったりと、さまざまな問題があるためです。
そこで倉敷市はファンド組成や運営を金融商品取引業者の資格をもつ民間企業に委託し、ファンド型クラウドファンディングの組成や運営を任せる形でこの問題を克服しています。すでに複数件の事業がファンドの支援を受けており、竹林問題や伝統農作物の継承などが事業によって進められています。
倉敷市は民間企業にファンドを任せるのではなく、支援する事業の審査に参加するなどの影響力を確保しており、ファンド形成にかかる経費の助成という形で支援を行っています。
地方の未来を変える!自治体クラウドファンディングの可能性と展望
自治体によるクラウドファンディングは、地域活性や課題解決、住民参画の推進など、行政だけでは対応しきれない分野で新しい可能性を生み出しています。今後さらに、スポーツ・文化・医療・教育・観光など分野を問わず自治体主導のプロジェクトが拡大すれば、地域住民だけでなく全国から多くの支援・協力が集まり、持続的なまちづくりが実現できるようになるでしょう。
ひと昔前までは、自治体職員がファンドについて考えることなどありませんでした。しかし昨今は自治体の役割が増え、業務領域も急速に拡大しているため、自治体単独の努力では追い付けないレベルになっているのではないでしょうか。
サイネックスは「官民協働による地域創生 」をテーマに、DXやシティプロモーションなどの事業を通して自治体のご支援をしています。また、自治体職員の方々の業務にもスポットを当てて、先進的な取り組みの裏にある努力を紹介する取り組みもしています。シティプロモーションアワード2023金賞を受賞した羽村市の職員の方へのインタビューなど大変参考になります。ぜひあわせてご覧ください。
シティプロモーションアワード2023金賞受賞!! 羽村市のシティプロモーションの取り組み(前編)
シティプロモーションアワード2023金賞受賞!! 羽村市のシティプロモーションの取り組み(後編)








